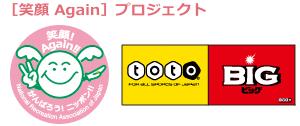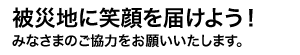被災地に笑顔を届ける
[笑顔!Again!]プロジェクト
公益財団法人日本レクリエーション協会は、東日本大震災で被災された方たちへ、レクリエーション活動を通して、こころとからだのケアを行うとともに、人とのふれ合いを育むプログラムを実施しています。
また、子どもたちへはあそびやスポーツを通して楽しみながら身体を動かすプログラムの提供を行います。
多くの方々に笑顔をお届けする[笑顔!Again!!]プロジェクト、活動状況はこちら。

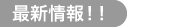
2012.3.18 「高齢者を対象としたレクリエーション・ボランティアセミナー」開催
2012.3.13 大船渡市のサロン活動を支援 岩手県レクリエーション協会
2012.2.26 「心とからだのリフレッシュ教室」開催 岩手県宮古市レク協会
2012.2.24 住田町で高齢者の健康づくり 遠野市レクリエーション協会
2012.2.20 仮設入居者に笑顔を 福島市レクリエーション協会
2012.2.11 Vision of the team recrew—震災レク支援のこれから―レクリエーション支援の方向を考える
2012.1.14 カラダが動いてきた! 山田町大沢仮設団地集会所 岩手県レクリエーション協会
2011.10.25~31 あなたに会えて良かった!たくさんの笑顔をありがとう! 笑顔宅急便IN福島(復興支援ボランティア活動報告)
2011.12.16 被災者に寄り添う支援活動をめざして おおさきレクリエーション協会(宮城県)
2011.11.30 一つずつ「日常」を取り戻すために。岩手県大槌町
2011.11.23 南相馬市の子どもたちが「あそびの城」に参加しました。伊達市レクリエーション協会
2011.11.5 17回の活動に553人が参加 遠野市レクリエーション協会
2011.11.12 福島県相馬市で「あそびの城inそうま」が開かれました。
2011.11.6 宮古市レクリエーション協会が高浜仮設団地で「ふれあい健康教室」を行いました。
2011.10.20 大東町レクリエーション協会が陸前高田市で支援活動を始めました。
2011.10.8 仙台市レクリエーション協会の仮設住宅支援が始まりました。
2011.9.18 福島県レクリエーション協会が飯舘村仮設住宅を訪問しました。
2011.9.4 いわて子どもあそび隊が田野畑村「親子ふれあい広場」で活動しました。
2011.8.28 福島民報、福島民友新聞にネイチャー&レクリエーション楽宿の様子が掲載されました。
2011.8.20 仮設住宅に住む浪江町のみなさんと楽しい一時を 福島市レクリエーション協会
2011.8.20 仮設住宅での活動が始まりました! しちがはまレクリエーション協会(宮城県七ヶ浜町)
2011.8.19 宮城県レクリエーション協会が石巻市鮎川地区の避難所で行ったレクリエーション・ボランティアの様子(動画)をUPしました。
2011.8.9 【詳報~その3~】ネイチャー&レクリエーション楽宿の実施状況
2011.8.9 【詳報~その2~】ネイチャー&レクリエーション楽宿を支えたスタッフ
2011.8.9 【詳報~その1~】全日程終了!! ネイチャー&レクリエーション楽宿
2011.8.7 福島県レクリエーション協会 放射線を気にせず、伸び伸びキャンプ!
2011.8.7 宮城県レクリエーション協会 女川町の子どもたちが鬼首スキー場で野外活動を楽しみました
2011.8.6 【速報】ネイチャー&レクリエーション楽宿 第2期終了
2011.8.3 【速報】ネイチャー&レクリエーション楽宿(がっしゅく)スタート!!
2011.7.20 八戸市レクリエーション協会、岩手県野田村でレク・ボランティア
2011.7.17 遠野市レクリエーション協会、柏木平レイクリゾートでレク支援
2011.7.17 陸前高田市立横田小学校の親子が遠野市に遊びに来ました。
2011.7.12 八戸市レクリエーション協会、岩手県野田村でレク・ボランティア
2011.6.29 課程認定校青森県八戸短期大学の学生の皆さんが、岩手県野田村でレク・ボランティア活動
2011.6.05 福島県うつくしま情報局、福島県レクリエーション協会のレク・ボランティア活動を放映
2011.5.28 久慈市レクリエーション協会が全国あそびの日キャンペーン”集まれ久慈っ子 チャレンジ広場”を行いました
2012.2.11
Vision of the team recrew—震災レク支援のこれから―
レクリエーション支援の方向を考える
評価されるレクリエーションによる支援
時間が経つのは早いもので、東日本大震災の発生から1年が経過しました。昨年11月号にて震災後半年間でレクリエーション協会関係者の支援活動が400を超えることをお伝えしました。その後、活動の場は避難所から仮設住宅の集会所等へと移り、活動の頻度は落ち着いてきましたが、岩手県、宮城県、福島県では定期的な活動が続いており、1年間の活動は550近くに上ると思われます。
昨年の4月から被災地での取材を始め、この誌面で活動の様子をレポートしてきましたが、現場では「今、動かなければレクリエーション協会ではない」という言葉をよく耳にしました。おそらく、活動を支えた方々に共通する気持ちだと思います。震災当初の活動は被災地へと向かう道路の状況も悪く、避難所では活動するスペースの確保や沈んだ気持ちの方々への声かけなど、難しい面も多々ありましたが、そうした困難を乗り越える皆さんの決断力、行動力に頼もしさを感じてきました。
レク関係者の支援の特徴は、なんといっても被災者の方々と積極的にコミュニケーションを取っていることです。体操やちょっとした遊び、クラフトなどをするときも、参加者の中にスタッフも入って一緒に楽しむ。また、参加者同士が一緒に何かをする場面を作り、顔見知りになり、会話が生まれ、コミュニケーションが深まるように支援活動を展開していました。また、そうした展開がしやすいように、声を出したり、笑いがおきるようなゲームやアクティビティを活動の始めに行っていました。その結果、支援活動の現場では和やかな雰囲気が広がり、たくさんの笑顔と出会うことができました。
今回の震災ではレクリエーションによる支援への評価もされています。例えば、ある医療ネットワークは、「頭に溜まったストレスは、子どもも大人も、声を出したり、リズムに乗って身体を動かしたり、手をつないだりするなどレクリエーション的なアプローチが有効」として、自分たちの支援活動の中にもレクリエーションを取り入れています。また、介護予防や健康体操的な活動への参加者が減ってしまったため、「楽しみながら運動ができないか」とレク協会による支援活動を取り入れた被災地もありました。

問われるレクリエーション支援の幅
一方で、レクリエーションによる支援の課題も見えてきました。例えば、震災当初、もちろん避難所ではレクリエーション支援のニーズはあったのですが、地域によっては泥のかき出し等へのマンパワーが求められていました。自分たちの得意分野の支援よりもそちらを優先していたNPOや企業も多く、レク関係者でもそうした支援活動に参加した方がいました。そうした団体、レク関係者は、被災地とのつながりを作り、その後の得意分野を活かした活動をスムーズに展開しています。レクリエーション協会としてこうしたニーズへも対応すべきか。今後の検討課題です。
被災地の災害ボランティアセンターには、日中の子どもたちの遊び相手や高齢者の話し相手などを求めるニーズも寄せられていました。結果的にはこうしたニーズにレク協会として対応することはできませんでしたが、細かなニーズへの対応と、傾聴や会話、託児など、レク支援の幅をどうとらえていくかの検討も必要です。
「被災者の生活がより豊かに」という視点からは、例えば、流された写真などの思い出の品を整理・洗浄する活動や、仮設住宅での生活を彩るためのモノ作り、園芸、買い物等の外出、そのための身だしなみや化粧等への支援など、幅広い支援活動が行われています。今後は、そうした支援も視野に入れて活動をする必要がありそうです。

つながりと生活の再創造(re-create)
そして今、レクリエーションによる支援活動には、2つのことを再創造=re-createしていくことが求められています。一つは、人と人のつながり、コミュニティーの再創造です。仮設住宅には地域ごとに住む配慮もされていますが、そうでない場合も多く見られ、高齢者の孤立・閉じこもりが課題となっています。また、これまで三世代が同居していた家族が、仮設住宅等で別れて住む「世帯分離」が進んでいるというデータもあります。これから2年以上過ごすであろう仮設住宅等の新しい生活環境の中で、新たな人と人のつながりを作る支援が求められていますし、そうしたコミュニティー作りに住民自らが取り組むための支援も必要だと考えられています。
もう一つの課題は、震災前の生活を取り戻していくための支援です。ある被災地での調査で、買い物で調理済みの食品が多く買われているデータが出ていました。これは自宅で料理をしなくなっている状況を推測させますし、実際に「料理の仕方を忘れてしまった」という話も聞かれます。避難所や仮設住宅での生活を通して、震災前の生活習慣や力を発揮していたことが失われているのです。
中越地震の際にも同じことが起こりました。この時、レク支援の中で地域の食文化を楽しむ活動を入れたところ、参加者が毎回ちょっとした手料理を持ちよるようになり、料理をする習慣が戻ってきたというケースがありました。レクリエーションの中で、食文化、手仕事文化、農林漁業の知恵・技術を楽しむという視点を持つことで、生活を取り戻す支援ができるのです。そこで楽しむ活動は、子どもたちや被災地を訪れる人々にとっても楽しい体験や学習の機会となり、作り出される物は地域の観光資源にもなっていく可能性があります。そうした過程の中で、支援を受けていた被災者は子どもたちの育成や地域作りの担い手になっていくでしょうし、子育て支援、教育、観光等の中で復興に向けたレク支援の新たな役割が広がるのではないかと思います。
もちろん被災地でのレク支援の課題はこれだけではありません。放射線の問題で外遊びが制限されたり、津波の被害で遊び場がなくなったりしている状況から、子どもたちの運動量が著しく落ちているというデータもあります。月刊レクルーでは2年目に入った被災地での活動をレポートするとともに、レク支援の課題や今後の向かうべき方向も考えていきます。
(企画・広報チーム 小田原一記)